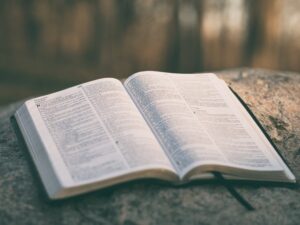創世記22:1-24「主が見てくださる」
カナンの地にあって
この箇所は、アブラハム物語の中で最も有名と言ってもよいエピソードです。この物語は、ユダヤ人の伝統では「アケダー」と呼ばれています。ヘブル語で「縛り」を意味することばです。9節に出てくる「息子イサクを縛り」という表現から来ています。一つの物語に特定の呼び名がついていることからも、この物語がいかに人々に強烈な印象を抱かせてきたかが分かります。
そして実は、この物語に対する批判というのも歴史の中で繰り返されてきました。理由はみなさん推測できると思います。子どもをささげることを命じるなんて、そんな神はおかしい。アブラハムはむしろここで抗議をするべきだった。そういった批判は昔からあります。また、この物語は子どもへの虐待を正当化する危険性をもっているという批判もあります。神さまのためなら、子どもの命を犠牲にしてよいのか。とても受け入れることができない。確かにそうです。私自身、もし自分にこんなことが命じられたら一体どうするのか。想像したくもありません。恐ろしいこと。
ただ、そういった批判の前に私たちが理解しておかなければならないのは、この物語が記された当時の宗教事情です。実は当時のカナンの地において、神々に子どもをささげるという儀式はよく知られていました。アブラハムもよく知っていたはずです。特に有名なのは、モレクという神に対する儀式で、聖書の中にも度々登場します。そして列王記や歴代誌、エレミヤ書、エゼキエル書などを見ると、なんとイスラエルもその影響を受けていたと書かれています。神さまは預言者たちを通してそれを厳しく非難しています。非常に厳しく非難している。そういった背景を踏まえると、このアケダーの物語は決して、子どもの命を犠牲にすることを推奨しているわけではないというのは明白です。むしろ逆です。「その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない」、神さまは御使いを通してはっきりと仰っています。神さまは子どもをささげられて喜ぶようなお方では決してない。むしろそれを忌み嫌っておられる。その証拠に、この後のレビ記や申命記では、子どもをモレクにささげるという行為が厳しく禁じられていくことになります。
信仰者の試練
では、神さまはなぜ自らが忌み嫌っておられることをここで命じたのか。1節を見ると、「これらの出来事の後、神がアブラハムを試練にあわせられた」とあります。試練としてです。試練ということばは、「試み」に「練る」と書きます。苦難などの「試み」を通して、その人が「練られていく」、それが目的です。ふるい落とすためではありません。試験とは違います。神とともに生きる信仰者としてアブラハムが成長していくため、神さまはアブラハムを試練にあわせられた。このアケダーの物語は、試練の物語です。
けれども、当のアブラハムにはそれが分かりません。これを読んでいる私たちは、「試練にあわせられた」とありますので、「これは試練で、アブラハムは本当にイサクをささげる必要はないんだ」という前提で読み進めることができますが、アブラハムは違います。試練の中にある者は、自分が今直面しているのが試練だということは分かりません。ひたすら苦難、ひたすら災いです。そこになんの意味があるのかなど分からない。自分の成長のため、自分が練られるため、そんなこと考える余裕などありません。アブラハムは全く理解できなかったはず。「神さま、一体なぜですか。あなたが約束して、あなたが与えてくださったイサクですよ。一体なぜそのイサクをささげるように命じるのですか。一体あなたは何がしたいのですか。」神さまが分からない。神さまが見えない。信仰者が味わう苦しみがここにあります。神さまが自分の人生を導いてくださっている。神さまがこの世界を治めておられる。そう信じているからこそ、私たちの頭では理解できない出来事に直面したとき、私たちは苦しむのです。本当にこの神さまに従っていてよいのか。神さまから離れた方がもっと楽に生きられるのではないだろうか。信仰者だからこそ思い悩み、葛藤し、苦しみをおぼえる。
すぐに従うアブラハム
しかし、聖書はそのようなアブラハムの葛藤は一切描きません。葛藤しないはずがありません。神さまが与えてくださったひとり子です。しかしそれでも聖書は葛藤を記さない。ことばでは表すことができないということでしょうか。代わりに聖書が記すのは、神さまのことばに即座に従うアブラハムの姿です。3-4節「翌朝早く、アブラハムはろばに鞍をつけ、二人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼のささげ物のための薪を割った。こうして、神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目に、アブラハムが目を上げると、遠くの方にその場所が見えた。」ろばに鞍をつけ、薪を割り、遠くの方に山を見つけていく。アブラハムの小さな行動一つひとつから、思いが伝わってくるようです。
その後、ようやくアブラハムのことばが記されます。5節「それで、アブラハムは若い者たちに、『おまえたちは、ろばと一緒に、ここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き、礼拝をして、おまえたちのところに戻って来る』と言った。」最後の部分は原文を見ると、「私たちはあそこに行き、私たちは礼拝をして、私たちは戻って来る」、すべて「私たち」が付いています。「自分はイサクと一緒に行き、イサクと一緒に礼拝をし、イサクと一緒に戻って来る」、ということ。
また7-8節ではイサクとアブラハムがことばを交わします。「イサクは父アブラハムに話しかけて言った。『お父さん。』彼は『何だ。わが子よ』と答えた。イサクは尋ねた。『火と薪はありますが、全焼のささげ物にする羊は、どこにいるのですか。』アブラハムは答えた。『わが子よ、神ご自身が、全焼のささげ物の羊を備えてくださるのだ。』こうして二人は一緒に進んで行った。」
神ご自身がささげ物の羊を備えてくださる。アブラハムはどのような思いでそう答えたのでしょうか。私はこれまで、これはアブラハムの苦し紛れのごまかしだと思っていました。「お前がささげ物なんだ」とは口が裂けても言えない。だからアブラハムはここでごまかしているのだと。先ほどの「私たちは戻って来る」ということばもそうです。アブラハムはそう言うしかなかった。私はそう思っていました。
信仰の頂点
けれども今回改めて聖書を読む中で、私の読み方は変わりました。新約聖書を一箇所開きましょう。ヘブル人への手紙11章17-19節(新452)「信仰によって、アブラハムは試みを受けたときにイサクを献げました。約束を受けていた彼が、自分のただひとり子を献げようとしたのです。神はアブラハムに『イサクにあって、あなたの子孫が起こされる』と言われましたが、彼は、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は、比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのです。」
「私たちは戻って来る」、「神ご自身が、全焼のささげ物の羊を備えてくださる」、これはアブラハムの信仰のことばでした。苦し紛れのごまかしではありません。アブラハムは本気で信じていたのです。「『イサクにあってあなたの子孫が起こされる』、神さまは確かにそう約束してくださった。そしてその約束の通り、神さまはこんな年老いた私たちにイサクを与えてくださった。不可能を可能にしてくださった。その真実な神さまが、ご自分の約束をなかったことにするはずがない。何か道を用意してくださっているはず。それが何かは分からない。しかしそれでも私は神さまを信じ続けるんだ!」アブラハムはここで、神さまを信じる選択をしたのです。イサクを縛り、祭壇の上に載せ、刃物を振り上げたそのときも、アブラハムの信仰は揺らぎませんでした。「たとえ今ここでイサクの命が失われたとしても、神さまは必ずイサクをよみがえらせてくださる。神さまはそれができるお方だから。」アブラハムは最後の最後まで神さまの真実を疑いませんでした。
これまで私たちは、アブラハムの様々な姿を見てきました。立派な姿を見せたかと思いきや、神さまに信頼せず自分の浅はかな知恵に頼っていく、弱く不誠実な姿も多く見てきました。しかしそういった一つひとつの出来事を通して、彼の信仰は確かに養われ、成長していきました。そして約束の通りイサクが与えられるという出来事を通して彼はついに、神さまの真実を確信しました。そんな彼の信仰者としての歩みのある意味「総決算」として、神さまはこの試練を与えられた。そしてこの試練を通して、アブラハムの信仰はついにまばゆいばかりの輝きを見せるに至ったのです。「信仰の父」と呼ばれるアブラハムの信仰の頂点がここにあります。
アドナイ・イルエ
神さまはそんなアブラハムの信仰に確かに応えてくださいました。11-13節「そのとき、主の使いが天から彼に呼びかけられた。『アブラハム、アブラハム。』彼は答えた。『はい、ここにおります。』御使いは言われた。『その子に手を下してはならない。その子に何もしてはならない。今わたしは、あなたが神を恐れていることがよく分かった。あなたは、自分の子、自分のひとり子さえ惜しむことがなかった。』アブラハムが目を上げて見ると、見よ、一匹の雄羊が角を藪に引っかけていた。アブラハムは行って、その雄羊を取り、それを自分の息子の代わりに、全焼のささげ物として献げた。」
アブラハムが信じた通りに、神さまご自身が全焼のささげ物の羊を備えていてくださいました。神さまはやはり真実なお方だった。アブラハムの心はどれだけ平安で満たされたことでしょうか。アブラハムの思いは、その後の14節によく表れています。「アブラハムは、その場所の名をアドナイ・イルエと呼んだ。今日も、『主の山には備えがある』と言われている。」
「アドナイ・イルエ」、これは脚注にあるように、直訳すると「主が見てくださる」という意味です。「見てくださる」、これは単に見ておられる、監視しておられるということではありません。例えば、私が妻から「ちょっと子どものこと見ておいてもらえる?」と言われたら、それは単に座って黙って子どもを見ていればいいということではありません。お腹を空かせればご飯かおやつをあげ、気持ち悪そうにしていればオムツを替え、危ないことがないように絶えず先回りして動いていく、全て含めて「見る」です。絶えず一緒にいて、目を配り、必要に備えているということ。
「アドナイ・イルエ」、主が見てくださるとはそういうことです。私たちには理解できないこともあります。子どももそうです。なんでこの引き出しを開けちゃいけないのか分からない。なんでわざわざ苦い薬を飲まなきゃいけないか分からない。しかし親は、父なる神さまは全てを見ておられるのです。その上で、私たちを最も善い道へと、最も幸いな道へと導こうとしてくださっている。その父なる神さまに信頼し、私たちの歩みの全てをゆだね、神さまのことばに従っていく。それが信仰です。
摂理の信仰
このような信仰を、教会は長い歴史の中で、「摂理の信仰」と言い表してきました。「摂理」は英語で “providence” と言いますが、これは「前もって見る」という意味をもっています。神さまは私たちの、この世界の歩みを前もって見て、一切を導き、全ての必要を備えてくださっている。それが「摂理の信仰」です。この摂理の信仰を告白している大変美しいことばを最後にご紹介したいと思います。何度もご紹介しています、『ハイデルベルク信仰問答』の問26の答です。
わたしはこの方により頼んでいますので、
この方が体と魂に必要なものすべてを
わたしに備えてくださること、
また、たとえこの涙の谷間へ
いかなる災いを下されたとしても、
それらをわたしのために益としてくださることを、
信じて疑わないのです。なぜなら、この方は、
全能の神としてそのことがおできになるばかりか、
真実な父としてそれを望んでもおられるからです。(『ハイデルベルク信仰問答』吉田隆訳、新教出版社、1999年)
「たとえこの涙の谷間へいかなる災いを下されたとしても、それらをわたしのために益としてくださることを、信じて疑わないのです。」この摂理の信仰に立つとき、私たちはどんな試練も乗り越えることができます。全能の神であり、真実な父であるお方が、私たちの理解を超えたところで、全てのことを益としてくださる。全ての必要を備えていてくださる。アドナイ・イルエ、主が見ておられる。この信仰に私たちは立ち続けていくのです。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。