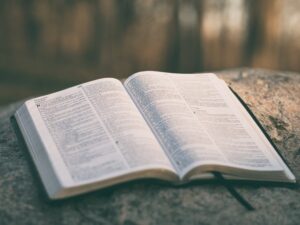エペソ5:19「主に向かって心から歌う」
序:賛美歌とは?
今日は10月の第一主日ですので、年間目標と年間聖句に関連するみことばに聴いていきます。はじめに、年間聖句をみなさんで読みましょう。「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です」(ローマ人への手紙12章1節)。この箇所から、「礼拝の民として生きる」という目標を掲げて、1年間の歩みを送っています。
前回は、礼拝の中で神のことばを聴くことの大切さについて、ネヘミヤ記8章のみことばに聴きました。礼拝の式次第の中でいうと、聖書朗読と説教です。今回、私たちがともに考えたいのは、賛美です。キリスト教会は、礼拝の中で多くの賛美歌を歌います。私たちの教会でも、開会の祈りの後に1曲、聖書朗読の前に1曲、説教と応答の祈りの後に1曲、今日の場合は聖餐式で1曲、献金の時に1曲、最後の「すべてのめぐみの」で1曲、合計6曲の賛美歌を1回の礼拝式の中で歌っています。そう考えると結構な数です。礼拝式全体の中で、賛美は大きな比率を占めていることがよく分かります。
では、そもそも賛美とは何でしょうか。古代の有名な神学者でアウスグティヌスという人がいますが、彼は賛美歌をこのように定義しています。「賛美歌とは、歌うことによる神への賛美である。賛美歌は、神への賛美を表現する歌である。賛美であっても、それが神に向かっていなければ賛美歌ではない。賛美で、しかもそれが神に向かっていても、歌わなければ賛美歌ではない。したがって賛美歌であるためには、三つのことがら—賛美、それが神に向かっていること、さらに歌われることが必要なのである。」
賛美であること、神に向かっていること、そして歌われること。この三つがそろってはじめて、賛美歌はまことの賛美歌となる。これは今の時代でも概ね通用する定義だと思います。そして、今日私たちが開いているエペソ人の手紙5章19節の内容ともちょうど重なってきます。ですからこの後の時間、先ほどの賛美歌の定義を手がかりとしながら、このエペソ5章19節のみことばをご一緒に味わっていきたいと思います。
賛美であること
まずは、「賛美であること」です。賛美歌が賛美歌であるためには、まずはそれが「賛美」でなければならない。当たり前のことですが、とても大事なことです。賛美とは、ほめたたえることです。では逆に、ほめたたえることのない賛美とはどういうものか。口は動いて、歌ってはいるけれども、実はただ文字と音を追っているだけ。式次第で決まっているから、みんなが歌っているから、それに合わせているだけ。歌いながらも、歌詞はまったく入ってきません。さっき歌った賛美歌が、何を歌った賛美歌だったのか、全く思い出すことができない。私自身、自分で言いながらドキッとしています。思い当たる節があるからです。ほめたたえることのない賛美、それは残念ながら、まことの賛美ということはできません。
そんな私たちに対して、聖書は何と教えているから。19節の最後、「心から賛美し、歌いなさい」。心から賛美し、歌うこと。それによって賛美歌はまことの「賛美」となっていく。
聖書にはよく、「新しい歌を主に歌え」というフレーズが出てきます。今日の招きのことばでもお読みしました。「新しい歌を主に歌え」。これは当然、毎週新しい賛美歌を作詞作曲しなければいけないということではありません。同じ歌を繰り返し歌ってはいけないということでもありません。そこで問われているのは、私たちの心です。たとえ慣れ親しんだ賛美歌であったとしても、メロディとともに、その歌詞のことば一つひとつに思いを巡らせるとき、その賛美歌は「新しい歌」として響いてくるはずです。神さまが私たちに何をしてくださったのか。イエス・キリストによってどれだけの恵みを注いでくださったか。神さまの御業を思うときに、私たちの内で感謝と喜びが新たにされていきます。その感謝と喜びが、私たち自身の内からあふれ流れていく。それが「心からの賛美」です。神さまが喜ばれるまことの「賛美」。
神に向かっていること
続いて二つ目。「神に向かっていること」です。エペソ5章19節にも、「主に向かって心から賛美し、歌いなさい」とあります。賛美歌を歌うとき、私たちは誰に向かって賛美をささげているのか。誰をほめたたえているのか。三位一体の神さま、ただお一人です。
これも当然のことです。みんな分かっていること。しかし先ほどと同じように、主に向かわない賛美というものが現実には存在します。当然、唯一まことの神さま以外の、異教の神々への賛美もありますが、そこにあえて触れる必要はないと思います。ここで私たちが注意したいのは、私たちが賛美歌を歌うとき、それが神さまにではなく、自分自身に向けられていることがあるのではないか、ということです。神さまそっちのけで、自分だけを喜ばせるための賛美、自分の栄光を表すための賛美というものがあるのではないか、ということ。
もちろん、喜んではいけないということでは決してありません。先ほどあったように、心から賛美するということは、そこに喜びが伴うということです。私たちの喜びが伴ってこその賛美です。けれども、自分を喜ばせること自体が目的となっているのであれば、それは神への賛美ではありません。あえて言えば、それは自分への賛美です。自分が気分よく、気持ち良くなるための賛美。あるいは、自分の美しい歌声によってみんなの注目を浴びたい、賞賛を浴びたい、そのための賛美。そのような私たちの賛美を、神さまは喜ばれるでしょうか。
今日の礼拝式では私が司会をしていますが、私が司会をするときにいつも気をつけていることの一つに、賛美の前の呼びかけのことばがあります。「聖歌総合版〇〇番を歌いましょう」ではなく、「聖歌総合版〇〇番をもって主を賛美しましょう」。多少バリエーションはあると思いますが、「主を賛美しましょう」「主をほめたたえましょう」と呼びかけることをいつも大切にしています。私たちはただ単に賛美歌を歌うのではない。この賛美歌をもって、主を賛美し、主をほめたたえるのだ!些細な表現の違いではありますが、そういった身近なところからも、私たちの賛美の姿勢をいつも確認し続けたいと思うのです。主に向かって賛美し、歌うこと。そこに私たちの喜びがあります。
歌われること
最後、三つ目。「歌われること」です。賛美歌は歌われるものである。これまた当然のことですが、一口に賛美歌を歌うといっても、そこには色々な形があります。今日の聖書の箇所でも、賛美の様々な形式が前提とされています。「詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい」。詩と賛美と霊の歌、三つのことばが出てきます。最初の「詩」は、特に旧約聖書の詩篇のことを指しています。次の「賛美」は、その時代に新しく作られていた賛美歌のことを指していると考えられます。新約聖書の中にも、マリアの賛歌であったり、ピリピ2章のキリスト賛歌と呼ばれるものであったり、古代の教会で歌われたであろう賛美歌がそのまま載っている箇所があります。最後の「霊の歌」が具体的に何を指しているのかはよく分かりませんが、より即興的な賛美歌のことを指しているのかな、などと私は想像します。いずれにせよ、この箇所が言いたいのは、「賛美歌には詩と賛美と霊の歌という三つの種類がある」ということではなく、賛美にはそれだけ豊かな形式があるのだということです。
また、19節に出てくる三つの動詞も賛美の形式の豊かさを表しています。最初の「語り合い」は、互いに歌い交わす交唱や、私たちの教会でもしている聖書の交読のことを意識していると考えられます。次の「賛美し」は、広くほめ歌を歌うこと全般を意味することばです。そして最後の「歌いなさい」は、語源的には、「弦をはじく」という意味をもっていまして、楽器演奏を表すことばでもあります。ですからこういった動詞からも、教会には初期の頃から、交唱という形式であったり、楽器を使ったり、使わなかったり、様々な賛美の形式が存在していたことが分かります。豊かな賛美の世界がそこにはありました。
そして今の時代、賛美の世界はいよいよ豊かになってきています。世界を見渡すと、そこには様々な賛美の形があります。例えば、プロテスタントの中には、「詩編歌」といって、詩篇に基づいた賛美歌を大切に歌い続けているグループがあります。また「無楽器派」といって、楽器を使わず、アカペラで歌うことを大切にしているグループもあります。あるいは私たちの身近でも、「聖歌」を使う教会、「讃美歌」を使う教会、「教会福音讃美歌」を使う教会、最近のいわゆるワーシップソングを歌う教会、パイプオルガンを使う教会、ピアノを使う教会、ギターやドラムなどのバンドを用いる教会、CDやヒムプレーヤーを使う教会、静かで厳かな雰囲気の中で歌う教会、元気に踊りながら歌う教会。様々な賛美の形があります。
そういった違いの背後には、それぞれの教会の伝統の違い、文化の違い、時代の違い、集う会衆の年代の違い、あるいは単純に好みの違いなど、色々な事柄が存在しています。私たちは時に、そういった違いが気になります。当然です。自分が慣れ親しんでいるものと違うものに遭遇して、違和感を感じるのは自然な反応です。私も数年前、南アフリカの礼拝に参加したときに衝撃を受けました。日本の多くの教会とは全然違う賛美の形がそこにはあった。
ただそこで大事なのは、異質なものを敬遠したり、拒否したりするのではなく、そこに豊かな賛美の世界を見ていくことです。もちろん、その賛美がまことの「賛美」であること、神に向かった賛美であることは大前提です。その上で、自分とは違った形だけれど、ここにも、主に向かって心から賛美をささげている人々がいる。神さまは確かに、この人々の賛美を喜んでおられる。豊かな賛美の世界をそこで感じ取っていきたいのです。
むすび
「詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し、歌いなさい」。心からの賛美をささげること。主に向かって賛美をささげること。豊かな賛美をささげていくこと。三つの観点から、賛美についてみことばに聴いてきました。この後私たちは早速、主に賛美をささげます。494番「いざみなきたりて」。1番にはこうあります。「いざ皆 来たりて 喜ばしく 声を一つにし ほめたたえよ 子羊イェスにみさかえあれや ハレルヤ!ハレルヤ!ハレルヤ!アーメン!」
今日ここに集った私たちが一つになって、喜びのうちに、子羊イエスの御名をほめたたえていく。神さまはそのような私たちの賛美を喜んで受け取ってくださいます。そして私たちの賛美を通して、この世界に神さまのすばらしさが、神さまの栄光がいよいよ現されていく。この後もともに、主に向かって心から賛美し、歌っていきましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。