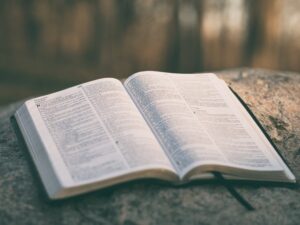ネヘミヤ記8:1-12「神のことばを土台として」
序:礼拝の中心
今日は9月の第一主日ですので、年間目標と年間聖句に関連するみことばに聴いていきます。はじめに、年間聖句をみなさんで読みましょう。「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です」(ローマ人への手紙12章1節)。この箇所から、「礼拝の民として歩む」という目標を掲げて、1年間の歩みを送っています。
前回は、なぜ私たちは日曜日に集まって礼拝をささげるのかについて、ともに考えました。私たちはイエス・キリストが復活された主の日の朝に、ともに集まり、復活の主を礼拝する。それが、私たちが毎週ささげているこの主日礼拝です。
私たちがささげる主日礼拝には、決まった式次第があります。前奏から始まり、後奏、報告に至るまでの流れが決まっています。その中で行われていること一つひとつはすべてとても大切なものですが、あえて、礼拝の式次第の中心はどこにあるかと問われたら、皆さんはどう答えるでしょうか。「私は賛美が一番好き」、「私は祈りが一番好き」。そういった個々人の思いはあるかもしれません。しかし、私たちが属するプロテスタント教会の流れでは、礼拝の中心として「神のことば」が大切にされてきました。具体的には、神のことばである聖書の朗読と、神のことばの説教です。
それは時間配分にも表れていまして、私たちの教会では聖餐式がない場合、礼拝式の長さは大体1時間くらいですが、その内約半分の30分弱が聖書朗読と説教に割かれます。あるいは教会によっては、説教が40分、50分、1時間と続くところもあります。それだけ「神のことばに聴く」ということに重きを置いている。そこに礼拝の中心があるからです。
神のことばを土台として
今日私たちが開いているネヘミヤ記8章は、そういった神のことばを中心にした礼拝の最初期の実践を記録しています。今の私たちの礼拝スタイルの原点がここにあるわけです。
まず確認しておきたいのは、この箇所の時代背景です。ネヘミヤ記というのは、バビロン捕囚から解放されたユダヤ人たちの状況を記録している書物です。かつて、神さまに対する罪ゆえにバビロンに捕囚に連れていかれ、異国の地で苦しい生活を送っていたユダヤ人たち。そんな彼らがついに解放され、祖国の地に戻ってくることができた。そこで彼らがまずしたことは、神殿の再建と、エルサレムの町の城壁の再建でした。その途中には、周囲の人々からの妨害に遭うなどの様々な困難がありましたが、最終的に神殿と城壁は無事に再建されます。ただ、それで一件落着ではありませんでした。町としての体裁はある程度整ったかもしれませんが、肝心の人々は何も変わっていません。見てくれは多少良くなったとしても、肝心の人々の生き方が変わらなければ、結局は捕囚前と同じことの繰り返しになってしまいます。
そこで、彼らはどうしたか。神のことばに聴いたのです。1-3節「民全体が、一斉に水の者の前の広場に集まって来た。そして彼らは、主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持って来るように、学者エズラに言った。そこで、第七の一日に祭司エズラは、男、女、および、聞いて理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持って来て、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで、男、女、および理解できる人たちの前で、これを朗読した。民はみな律法の書に耳を傾けた」。
ここに出てくる「モーセの律法の書」は、モーセ五書(創世記・出エジプト記・レビ記・民数記・申命記)のことを指していると考えられます。律法の専門家であるエズラという人が、その律法の書を持って来て、夜明けから真昼まで朗読を続けた。少なく見積もっても5時間ほどでしょうか。現代の私たちにはとても耐えられない時間の長さですが、民は一生懸命耳を傾けました。自分たちはこれから何を土台として歩んでいくのか。何を基準として生きていくのか。誰のことばに聞き従っていくのか。彼らは祖国の地で再出発をするにあたって、神のことばに聴くことを大切にしたのです。
私たちの教会の役員会では昨年から、山崎龍一さんという方が書いた『教会実務を神学する』という本を用いて学びをしています。教会の実務的な働きを聖書の価値観からどのように考えるのかについて、丁寧に手解きをしてくれる大変優れた本です。
その本の中で繰り返し問われているのは、知らず知らずの内に、教会に聖書以外の規範が入り込んではいないだろうか、ということです。「世間ではこう言われているから」、「私たちはこれまでずっとこうしてきたから」、「あの先生がこう言っていたから」、「私の経験上、こうした方がいいから」。世間の常識、教会の伝統、偉い先生のことば、個々人の経験が、教会の規範となっていないだろうか。もちろんそういったもの自体が悪いわけではありません。しかしそれが教会の規範となってしまっては、教会は教会ではなくなってしまいます。世の中一般の会社、サークル、同好会と何ら変わらない存在になってしまう。
教会の唯一絶対の規範は、神のことばなる聖書です。だから私たちは毎週集まって、一緒に聖書のことばに聴いています。聖書の勉強をするだけなら、個々人でしたらいいのです。家で聖書を読んだり、神学書を読んだり、ネット上の動画を見ていれば、聖書の学びはできます。それは大事なことです。しかし、それだけでいいということは決してありません。ともに集まって、一緒に同じ聖書のことばに聴くこと。それを通して私たちは、教会が拠って立つ土台を確認し続けるのです。今日の箇所でも、1節に「民全体が、一斉に集まって来た」とあります。私たちはこれから何を土台として歩んでいくのか。民全体が集まって、一生懸命神のことばに耳を傾けた。ここに、神の民の姿があります。神の民は、教会は、神のことばによってのみ建て上げられていく。だから、「神のことば」が礼拝の中心なのです。
神のことばの力
さて、エズラによって律法の書の朗読がなされた後、レビ人たちがその意味を解き明かすということをします。8節「彼らが神のみおしえの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解した」。これは、今でいう説教です。当時の人々にとっても、モーセ五書は何百年も前に書かれた書物でしたから、そのままでは理解できない箇所がたくさんありました。ですからレビ人たちがその一つひとつを丁寧に解き明かすことによって、人々は神のことばを理解しました。
けれどもそこで、私たちからしたら意外とも思える反応が起こります。9節「総督であるネヘミヤと、祭司であり学者であるエズラと、民に解き明かすレビ人たちは、民全体に向かって言った。『今日は、あなたがたの神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。』民が律法のことばを聞いたときに、みな泣いていたからである」。喜びの涙を流したのではありません。悲しみのあまり泣いていた。一体なぜか。自分たちの罪が示されたからです。「私たちの先祖が捕囚に連れて行かれたのは、この神のことばに聞き従わなかったからだ。そして自分たちは今もなお、神さまのみこころから遠く離れたところにいる。なぜ私たちはこんなすばらしい神のことばを蔑ろにし、異教の神々に頼っていったのか。」人々は、神のことばによって自分たちの罪の大きさを示され、悲しみ泣いたのでした。
これが、神のことばの力です。私たちは通常、自分を励ましてくれることば、癒してくれることばを求めて聖書を開きます。それは当然と言えば当然です。何も悪いことではありません。けれどもそこで覚えておきたいのは、聖書は私たちをいい気分にさせるためだけの書物ではないということです。もちろん、聖書は励ましのことば、癒しのことばに満ちています。しかし同時に、私たちの最も醜い部分を、罪を徹底的に暴き出すことばにも満ちています。
ヘブル書4章12節にはこうあります。「神のことばは生きていて、力があり、両刃の剣よりも鋭く、たましいと霊、関節と骨髄を分けるまでに刺し貫き、心の思いやはかりごとを見分けることができます」。私たちを鋭く刺し貫き、心の中の秘めた思いやはかりごとをすべて明らかにする。神のことばにはその力があります。神のことばを前にして、心が痛み、悲しみのあまり涙を流す。それは、その人が神のことばに真剣に聴いていることの証しです。神のことばと本気で向き合っていることのしるし。神のことばは私たちを、罪の告白と真実な悔い改めへと導きます。
主を喜ぶこと
それは私たちが決して避けて通ってはいけないことです。必ず通らなければならない道。しかし、そこで終わってもいけません。自分たちの罪を嘆き悲しむ民に対して、ネヘミヤたちは語りかけました。10節「行って、ごちそうを食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を贈りなさい。今日は、私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことは、あなたがたの力だからだ」。
たしかに、彼らは過去に大きな罪を犯しました。そして今もなお、神さまのみこころから遠く離れたところにいる。けれども、そんな罪深い民を、神さまは捕囚から解放し、祖国の地へ連れ戻してくださったのです。彼らは、神さまの豊かなあわれみをすでに受けている。その神さまの恵みの事実に目を向けようではないか。主の御業をみなで喜び祝おうではないか。ネヘミヤは人々を励ましたのです。
この後、私たちは聖餐にあずかります。その中で途中、黙祷の時間があります。神の御前に自分自身を深く吟味するときです。神の御前に自分自身を吟味するとき、そこで見えてくるのは、自分自身の罪深さです。救いを受けるには到底値しない、醜く弱い罪人の姿が見えてくる。私たちが避けて通ってはいけないことです。罪人としての自分の姿を直視しなければならない。
しかしそこで、神さまの招きのことばが聞こえてくるのです。「愛する兄弟姉妹たち。主イエス・キリストを神のひとり子である救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼して、キリストのしもべとしてふさわしく生きる志のある者はすべて、この食卓に招かれています。たとえ罪のとがめや良心の呵責を覚えたとしても、それを覆って余りある神の恵みに信頼し、信仰をもって聖餐にあずかってください。」
こんな私のために、イエス・キリストは十字架にかかってくださった。そのキリストの御業によって、今私たちは、神の国の食卓へと招かれている。私たちの罪がどれだけ深かろうと、それを覆ってなお余りある豊かな神の恵みがある。この恵みの事実を、救いの事実を、私たちは喜び祝うのです。この聖餐を通して、そして毎週の主の日の礼拝を通して、喜び祝う。それが、私たちの生きる力になります。「主を喜ぶことは、あなたがたの力だからだ」。神のことばによって建て上げられ、神のことばによって悔い改めへと導かれ、神のことばによって生きていく力が与えられる。今日も、そしてこれからも、神のことばにともに聴いていく教会でありたいと願います。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。