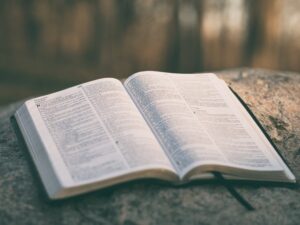2コリント5:17「主の日を喜び祝う」
序
今日は月に1回の、年間目標と年間聖句に基づく説教です。はじめに、年間聖句をみなさんで読みましょう。「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です」(ローマ人への手紙12章1節)。この箇所から、「礼拝の民として歩む」という目標を掲げて、1年間の歩みを送っています。
今日、私たちがともに考えたいのは、教会が日曜日に集まって礼拝をささげることの意味です。なぜ私たちは、1週間(7日間)ある中で、わざわざ日曜日に集まって礼拝をささげるのか。一体そこにはどのような意味があるのか。
イエス・キリストが復活された日
教会が日曜日に集まるのは、日曜日が休日で一番集まりやすいから、ではありません。現在、イスラム圏を除く多くの国では日曜日が休日となっていますが、この慣習がいつから始まったか皆さんご存知でしょうか。私は今回調べて初めて知ったのですが、日曜日を公的な休日としたのは、紀元321年のローマ帝国が初めてだったようです。ローマ帝国でキリスト教が公認されたのはその8年前の紀元313年ですから、そこには間違いなくキリスト教の影響がありました。ただそれと合わせて、当時のローマ帝国では太陽崇拝が広く行われていたようでして、その影響もあって、「太陽の日」である日曜が休日と定められたと考えられています。
いずれにしても、教会は日曜日が公的な休日になる前から、もっと言えば、教会はその最初期から、日曜日に集まって礼拝をささげることを大切にしてきました。それはなぜか。理由はただ一つ。イエス・キリストが復活された日だからです。
新約聖書には福音書が四つありますが、その四つすべてが、イエスさまは週の初めの日である日曜日に復活されたことを証言しています。今日、みなさんにお配りしている関連聖書箇所のプリントをご覧ください。今日は聖書箇所をたくさんご紹介したいと思っているので、一枚のプリントにまとめておきました。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、どの福音書もはっきり「週の初めの日」と言っていることが分かると思います。これは明らかな強調です。イエス・キリストは週の初めの日、日曜日に復活された!福音書はこの事実を何としても伝えようとしているのです。
週の初めの日に集まる教会
そしてイエス・キリストが天に昇られた後、教会はその「週の初めの日」に集まって礼拝をささげるようになりました。関連聖書箇所の⑤をご覧ください。使徒の働き20章7節にこうあります。「週の初めの日に、私たちはパンを裂くために集まった。パウロは翌日に出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。」これはユテコという青年が、パウロの話があまりにも長くて、眠さのあまり窓から落ちてしまうというエピソードの箇所です。彼らはいつ集まっていたのか。「週の初めの日」です。使徒の働きの中で、土曜の安息日を除いて、特定の曜日に言及しているのはこの箇所だけです。「パウロは◯曜日に〇〇をしました」という日誌ではありませんから、基本的に曜日の情報は必要ないわけです。ただここではあえて「週の初めの日に、私たちはパンを裂くために集まった」と言っている。「パンを裂くため」、これは今でいう聖餐式です。パウロの説教もありました。彼らはそのような集まりを、週の初めの日である日曜日に、おそらく定期的にもっていた。はじめに言いましたように、当時はまだ休日ではありませんから、仕事が終わった後、夕方以降に集まっていたのでしょう。日曜日に集まることを大切にしていた最初期の教会の姿がここにあります。
またもう一箇所、パウロが書いた手紙の中では、第一コリント16章2節に「週の初めの日」への言及があります。関連聖書箇所の⑥です。「私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなたがたはそれぞれ、いつも週の初めの日に、収入に応じて、いくらかでも手もとに蓄えておきなさい。」週の初めの日に献金を手もとに蓄えておきなさいというパウロの勧めです。この箇所から、コリント教会では、週の初めの日にみなが集まり、その中で献金も行われていたことが想像されます。先ほどの聖餐式、説教だけでなく、献金も行われていた。イメージが湧いてくると思います。
「主の日」の礼拝
そして、週の初めの日に集まる習慣が定着していくにつれて、この日は特別な名前で呼ばれるようになりました。私たちが今も使っている名前です。週報の式次第をご覧ください。一番上に「8月第1主日」とあります。8月の第一の「主の日」。この「主の日」です。関連聖書箇所の⑦をご覧ください。ヨハネの黙示録1章10節にこうあります。「私は主の日に御霊に捕らえられ、私のうしろにラッパのような大きな声を聞いた。」ヨハネの黙示録は紀元90年代の中頃に書かれたと考えられています。その時期にはすでに、週の初めの日を「主の日」と呼ぶことが教会の中で定着していたようです。
実際、その後に書かれた様々なキリスト教文書を見ると、「主の日」という名称が広い地域で定着していた様子が分かります。参考として、関連聖書箇所のプリントの⑧に、『十二使徒の教訓』という、1世紀末または2世紀初頭に書かれたとされるキリスト教文書のことばを載せました(聖書のことばではないのでカッコに入れています)。「主の日毎に集って、あなたがたの供え物が清くあるよう、先ずあなたがたの罪過を告白した上で、パンをさき、感謝を献げなさい。」今日の私たちと同じような聖餐礼拝が「主の日毎」にもたれていたことがはっきりと分かります。私たちの教会で行なっている毎週の主の日の礼拝式は、キリスト教会が2,000年間ずっと大切にし続けている習慣なのです。2,000年間途絶えることなく、主の日の礼拝は毎週続けられている。これはすごいことです。ものすごいこと。神さまが教会の歴史を確かに守り導いてくださっていることを感じずにはいられません。
新しい世界を生きる
ここまで、なぜ教会は日曜日に集まって礼拝を献げるのかについて、新約聖書の証言をもとに、歴史的な観点から考えてきました。キリスト教会は、イエス・キリストが復活された週の初めの日に集まって礼拝を献げるようになった。主の日の礼拝の根拠はイエス・キリストの復活にあります。けれどもそこからもう一歩進んで考えたいのは、なぜ私たちはイエス・キリストの復活を毎週おぼえて礼拝をささげるのかです。それが私たちにとってどのような意味があるのか。単に「イエスさまが復活してよかったね」では終わらない、大切な意味がそこにあるわけです。
それを教えるのが、今日のメインの聖書箇所、第二コリント5章17節です。改めてお読みします。「ですから、だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」この「新しく造られた者」ということば。これは直訳すると、「新しい創造」という表現です。イエス・キリストの復活は、単にイエスさまお一人が復活されてそれで終わり、ではありません。それは神さまの新しい創造の御業の始まりでした。罪に支配され、闇に覆われていた古い世界。その古い世界を打ち破り、神と人が、そして人と人が、愛と平和のうちにともに歩む新しい世界がもたらされた。それが、キリストの復活という出来事です。そして、「だれでもキリストのうちにあるなら」、キリストを主と信じるものはすべて、その新しい世界に生かされている。御霊によって新しく造り変えられている!
今の世を生きていると、私たちは時折、その事実を忘れてしまいます。あるいはその事実に確信がもてなくなることがあります。神と人が、人と人が、愛と平和のうちにともに歩む新しい世界がもたらされた。それならなぜ、この世界にはこんな悲惨なことが満ちているのか。止むことのない戦争。各地で起こる凶悪な事件。貧困に、飢餓に喘ぐ人々。抑圧、差別に苦しむ人々。キリストによってもたらされた新しい世界はどこにあるのか。いつになったら完成するのか。希望を見失いそうになってしまう。
私たち自身を見てもそうです。「だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です」。それなのになぜ、私はこうも変わらないのか。変わらず人を傷つけ、変わらず欲望に負け、変わらず罪に振り回されている。一体御霊の働きはどこにあるのか。何にも変わっていないじゃないか。イエス・キリストがもたらした救いが分からなくなってくる。それが私たちの現実かもしれません。
しかし、希望を見失いそうになるたびに、救いが分からなくなるたびに、私たちは主の日に集まり、イエス・キリストの復活を喜び祝うのです。今の世だけを見ていると、自分自身だけを見ていると、確かに罪の力はあまりにも強い。闇はあまりにも深い。しかし、イエス・キリストは2,000年前、その手強い罪の力を、深い深い闇を打ち破り、この週の初めの日によみがえられた!この揺るがない救いの事実に、私たちは立ち戻っていくのです。復活の主を礼拝するたびに、自分たちが今、イエス・キリストによって新しい世界に生かされていることを思い起こし、確信していく。そして復活の主は、やがて再びこの世界に来られて、すべての罪と悪を完全に滅ぼし、新しい世界を、神の国を完成させてくださる。その希望を新たにしていくのです。それが、週の初めの日、主の日の礼拝です。
「ですから、だれでもキリストのうちにあるなら、その人は新しく造られた者です。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。」イエス・キリストが復活された主の日。今日もこの日を、ともに喜び祝いましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。