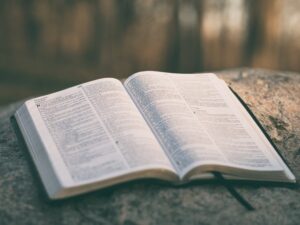創世記31:17-55「神のさばきの前で」
不穏な別れ
ヤコブがついにラバンのもとを旅立ちます。一人で故郷を出てから20年間過ごした地を離れるヤコブ。けれどもその旅立ちは決して、穏やかなものではありません。20節にはこうありました。「ヤコブはアラム人ラバンを欺いて、自分が逃げるのを彼に知られないようにした」。ラバンを欺いて逃げる。いわゆる「夜逃げ」同然の旅立ちです。本当なら、ヤコブもこんな旅立ち方はしたくなかったはずです。理想を言えば、「20年間お世話になりました!」「いやいや、20年間よく一生懸命働いてくれた。寂しくなるなぁ。故郷に戻っても元気に過ごしてくれよ。」そんな平和な旅立ちを望んでいたはず。しかし、そうはいかない現実があります。「故郷に帰るなんて、ラバンおじさんは絶対に許してくれない。けれども神さまは、『あなたの生まれた国に帰りなさい』と言われた。こうなったら、黙ってこっそり出ていくしかない。」苦渋の選択だったでしょう。しかし現実問題、そうするしかなかった。なんとも寂しい話です。
しかし、そのままで終わるはずがありません。ヤコブたちが逃げことを知ったラバンは、身内の者たちを率いてすぐに後を追いかけます。そしてなんとか追いつくと、ヤコブを責め立てます。26節「何ということをしたのか。私を欺いて、娘たちを、剣で捕らえられた者のように引いて行くとは」。ラバンの気持ちはよく分かります。ヤコブが一人でどっかに行くならまだしも、自分の娘や孫たちも黙って連れて行くなんて、あまりにもひどいじゃないか。ラバンとしては当然の怒りです。
けれども、神さまはちゃんと先手を打ってくださっていました。29節「私には、あなたがたに害を加える力があるが、昨夜、あなたがたの父の神が私に、『あなたは気をつけて、ヤコブと事の善悪を論じないようにせよ』と告げられた」。もしそのままいけば、ラバンは怒りのあまりヤコブに攻撃を仕掛けていたかもしれません。しかし、神さまが先回りして、夢の中でラバンに忠告してくださっていた。ラバンはこの20年間を通して、ヤコブとともにいる神さまがどれだけ力強いお方であるかを知っていました。ヤコブが神さまの特別な守りの中にあることをよく知っていた。ですからラバンは、神さまの忠告に素直に従います。従わなければもっと悪いことになると直感したのかもしれません。
濡れ衣?
ただ、話はそこで終わりません。ラバンは別の点をついてきます。30節「それはそうと、あなたは、あなたの父の家がどうしても恋しくなって出て行ったのだろうが、なぜ私の神々を盗んだのか」。この神々というのは、他の所でテラフィムとも呼ばれていますが、ラバンの家に代々伝わる守り神の像のことを指しています。いわゆる偶像です。それが家からなくなっている。お前が盗んでいったのだろう。なんてことをするんだ!ラバンはヤコブを責め立てます。
しかし、ヤコブからしたら完全な濡れ衣です。「もしそんなことをした奴がいたら、その者を生かしてはおかない!どうぞ好きなだけ調べてください。」ヤコブは確信をもって反論します。そこでラバンはヤコブの天幕、レアの天幕、二人の女奴隷の天幕を探しますが、見つかりません。最後にラケルの天幕も探しますが、そこでもやはり見つかりません。結局どこにも見つからなかった。
すると、ヤコブの怒りが爆発します。36節から「するとヤコブは怒って、ラバンをとがめた。ヤコブはラバンに向かって言った。『私にどんな背きがあり、どんな罪があるというのですか。私をここまで追いつめるとは。あなたは私の物を一つ残らず調べて、何か一つでも、あなたの家の物を見つけましたか。もしあったなら、それを私の一族と、あなたの一族の前に置いて、彼らに私たち二人の間をさばかせましょう。』」そしてそこから、この20年間、自分がどれだけ誠実に仕えてきたのかを語り始めます。私はあなたに一つも損をさせなかった。損失があっても、全部自分で負担をした。暑い中も寒い中も一生懸命頑張った。あなたは途中、何度も報酬を変えたけど、それでも私は忠実にあなたに仕え続けてきました。それなのに最後の最後まで私を疑うなんて、あんまりじゃないですか。これまで抑えてきたものが一気に溢れ出てきた。そんなヤコブの姿です。
しかし、この物語の面白いところは、ラバンの疑いは実際には濡れ衣ではなかったということです。実は、ヤコブが知らないところで、妻のラケルがテラフィムを盗んでいた。ラバンの追求は正しかったのです。なぜラケルが盗んだのか、理由はよく分かりません。父親であるラバンへの恨みから、最後に一矢報いてやろうと思ったのか、あるいはお守りとして手元に置いておきたかったのか。いずれにせよ、ラバンが追いついて、テラフィムを必死に探し回っていると聞いた時は、相当焦ったはずです。しかし、家の守り神をお尻の下に敷くという誰も予想できない方法によって、ラケルはピンチを脱します。ラケルはほっとしたことでしょう。けれども、ヤコブはそういったことを一切知りません。何も知らないまま、ラバンに対して自らの潔白を主直していく。
複雑な世界
こういった箇所を読みながら私が感じたのは、正しさって何なんだろうということです。ヤコブは、自分は正しい、何の落ち度もないと確信していました。だからこそ、「もし盗んだ奴がいたら、その者を生かしてはおかない」と大胆に言い放ちます。けれども、ラケルが盗んだことを知っている私たち読者は、「おいおい、そんなこと言って大丈夫なのか」と思うわけです。
幸い、ラケルの盗みはバレずに済みました。けれども、その後に続くヤコブの主張にも、危うさを感じずにはいられません。妻のラケルが盗みを隠し通した直後に、ヤコブは自らの正しさを主張している。知らなかったからしょうがない。それはそうです。けれども、ヤコブの自信と現実とのズレに、どこかモヤモヤする思いが残る。
また、ラバンのもとから黙って去るというヤコブの決断は本当に正しかったのかという疑問もやはり残ります。20節を思い出してください。そこで創世記の著者は、「ヤコブはアラム人ラバンを欺いて」と表現していました。これは元のヘブライ語では「ラバンの心を盗んだ」という表現です。その直前の、ラケルがテラフィムを「盗み出した」というのと同じことばです。事情は分かる。けれども、もっと穏やかに、平和の内に旅立つことは本当にできなかったのか。疑問が残ります。
いずれにしても、一つ言えるのは、この箇所は、ヤコブが100%正義で、ラバンが100%悪という単純な物語ではないということです。基本的にはヤコブが正しいでしょう。けれども、娘と孫を突然連れ去られて怒るラバンの気持ちはよく分かる。加えて、テラフィムを盗まれたというラバンの主張は事実その通りだった。どちらか一方だけが正しくて、どちらか一方だけが間違っている。現実はそんな単純ではありません。複雑な事情が入り組んでいる。それが人間の世界です。
事の善悪を論じないように
その複雑な人間の世界にあって、改めて目を留めていきたいのが、神さまがラバンに語られたことばです。24節「あなたは気をつけて、ヤコブと事の善悪を論じないようにしなさい」。「ヤコブが正しいから」とか、「ラバン、お前が間違っているから」とかではない。「気をつけて、事の善悪を論じないようにしなさい」。とても味わい深い神さまのことばです。
もちろん、善悪はどうでもいいということではありません。私たちは善を追い求め、悪を遠ざけるべきです。何が善で、何が悪か、見極めていかなければならない。とても大事なことです。
しかし、もう一方で心に刻んでおきたいのは、私たちは究極的には、善悪を論じることのできる立場にはないということです。なぜか。人はみな、不完全だからです。私たちは、この世界で起きているすべての事柄を把握することはできません。限られた視点、限られた視野でしか物事を見ることができない。また、物事を見る私たちの目自体がそもそも曇っている。私たちの思考そのものが大きく傾いている。人はみな、罪人なのです。そんな私たちが、どうして事の善悪を論じることができるでしょうか。私が正しい、お前が間違っている。どうして人をさばくことができるでしょうか。
完全に正しいお方はただお一人、神さまだけです。今日の箇所の最後で、ラバンとヤコブは契約を結びます。49-50節「われわれが互いに目の届かないところにいるとき、主が私とあなたの間の見張りをされるように。もし、あなたが私の娘たちをひどい目にあわせたり、娘たちのほかに妻をめとったりするなら、たとえ、だれもわれわれとともにいなくても、見よ、神が私とあなたの間の証人である」。主が私とあなたの間の見張りであり、神が私とあなたの間の証人である。ラバンとヤコブが最終的に行き着いたのはここでした。それぞれ思うことは色々とあったでしょう。問題がすべて解決したわけではありません。しかし両者とも、神さまの正しさに自らをゆだねることにおいて、一致点を見出したのです。その結果、ラバンとヤコブは和解を果たし、ともに食事をして、翌朝、ラバンは祝福を残して、自分の所へ帰っていきました。
正しさと正しさがぶつかり合う、複雑な人間の世界です。けれども、お互いが自分の不完全な正しさを握りしめている限り、そこには争いしか生まれません。お互いに対する不信感だけが募っていく。悲しいこの世界の現実です。私たちは、自分の正しさの限界を認めなければなりません。自分たちの不完全な現実を、罪人の現実を認めなければならない。その上で、神さまの正しさに信頼していきたいのです。自らの正しさを手放し、すべてを見ておられる、神さまの正しさにすべてをおゆだねしていきたい。その先に、和解が実現していきます。神さまだけがもたらすことのできる、真実な和解が実現していく。今日も私たちはともに、神さまの正しさの前に進み出ていきましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。