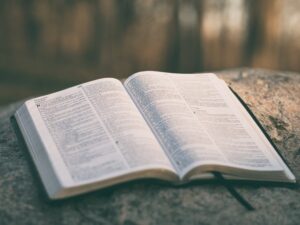創世記37:1-36「神の御手はどこに」
序
いよいよ今日からヨセフ物語です。この37章から最後の50章まで、ヨセフを中心とした物語が続いていきます。聖書の中で最もドラマチックな物語の一つです。主日礼拝の中では毎回大体1章ずつ分けて読み進めていきますが、ぜひみなさん、ご自身で一度通してヨセフ物語を改めて味わってみてください。全体を通して読むことによって、新たに見えてくることがたくさんあると思います。また毎週の礼拝の中でも、絶えずヨセフ物語全体の流れを意識しながら、1章1章じっくり味わっていきたいと思っています。
罪の連鎖
さて、このヨセフ物語は、創世記の他の多くの物語と同じように、家族の問題から始まっていきます。問題の原因は何か。父ヤコブの偏った愛、偏愛です。ヤコブが息子たち全員を同じように愛していたなら、何も問題は起こらなかったはずです。しかし3節にあるように、ヤコブは息子たちのだれよりもヨセフを愛していました。その理由として、「ヨセフが年寄り子だったからである」とありますが、加えて、ヨセフが最愛の妻ラケルの息子であったことも大きく関係しているはずです。ヤコブはヨセフだけに「あや織りの長服」をプレゼントするなど、明らかに特別扱いをしていました。当然、他の息子たちは面白くないわけで、4節には「彼を憎み、穏やかに話すことができなかった」とあります。
こう見ると、家庭崩壊の元凶は明らかに父ヤコブにあるわけですが、思い返せば、ヤコブ自身もそういった家庭で生まれ育ちました。父イサクは兄エサウを、母リベカはヤコブを特別に愛していた。エサウとヤコブが決裂したことの背景には、そういった歪な家庭環境がありました。ですから今回のことに関しても、もちろんヤコブの責任は重いわけですが、ヤコブ一人に原因を帰すことはできないと思うのです。ここで描かれているのは、罪の連鎖です。アダムとエバの家庭から始まり、ノアの家庭、アブラハムの家庭、イサクの家庭、どの家庭にも問題がありました。創世記は明らかに家庭の問題、兄弟関係の問題にフォーカスを当てています。最も近しい間柄でさえ、人は愛し合うことができない。そういう罪の現実を描こうとしているのです。罪の支配の中で生まれ育った人間は、なかなか罪の連鎖を断ち切ることができない。罪の被害を受けた者が、今度は罪の加害者になっていく。この世界の悲惨な現実がここでも描かれています。
ヨセフの未熟さ
また今日の箇所では、ヨセフ自身が家庭の問題をさらに複雑にしています。彼がもし思慮深く、慎ましい人物であったなら、お兄さんたちにここまで憎まれることはなかったはずです。しかし、ヨセフは未熟でした。いわゆる「空気が読めない人」だったようです。5節からは、ヨセフが見た二つの夢のことが書かれています。一つ目は畑でお兄さんたちの束がヨセフの束を伏し拝んだというもの。二つ目は、太陽と月と十一の星がヨセフを伏し拝んだというもの。意味は明らかです。解き明かす必要はありません。やがて、お兄さんたちや両親までもがヨセフにひれ伏すようになるということ。
創世記の中で夢というものは、神さまが人に語りかける手段として多く用いられています。神さまからの啓示です。ここでヨセフが見た夢も、実際に将来、エジプトで実現していくことになります。ですから、この夢自体は神さまが見させたものでした。しかし、ヨセフはそれを心の内に留めておくべきでした。あるいは話すとしても、お父さんだけにするべきだった。誰がどう考えても、お兄さんたちに話すべきではありません。しかし、ヨセフはそこまで考えなかったようです。17歳とありますから、それくらいの判断はできたはずですが、ヨセフはできませんでした。もちろん、だからと言って今回の悲劇はヨセフの自業自独だとは決して言えません。あくまでも悪いのはお兄さんたちです。けれども、このヨセフの思慮のなさが、お兄さんたちの憎しみに拍車をかけたというのは間違いなく言えることです。
「偶然」の重なり
そうして溜まりに溜まったヨセフへの憎しみが、ついにこの家族に悲劇をもたらしていきます。ただこの悲劇、よく見ていくと、まるで見えない力が働いているかのように、色々な「偶然」とも思える出来事が重なっていきます。まず、ヨセフはお父さんに使いを頼まれて、お兄さんたちを訪ねにシェケムというところにやってきます。けれどもシェケムに着いても、お兄さんたちは見つかりません。そのまま見つからなければ、ヨセフは諦めずに帰ったはずです。この後の悲劇は起こらなかったはず。しかしそこでヨセフは偶然、お兄さんたちが次の行き先について話しているのを聞いたという人に出会います。これは結構な確率だと思うのです。その結果、ヨセフはお兄さんたちがドタンというところに向かったことを知ります。
18節からは、物語がお兄さんたち目線で進んでいきます。ヨセフが近づいているのを見たお兄さんたちは、日頃の鬱憤を晴らす機会だと重い、ヨセフを殺す計画を立てます。けれどもそれを聞いた長男のルベンは、さすがに殺すのはマズいと思い、枯れた井戸に投げ込むことを提案します。後からこっそり助けようと考えたようです。ルベンは以前、父ヤコブの側女と不倫関係をもって、ヤコブにそれが知られたということがありましたから、これ以上父の怒りを買うようなことがあってはいけないと思ったのかもしれません。
いずれにせよ、お兄さんたちはルベンの提案通り、ヨセフを捕らえて穴に投げ込みます。それから座って食事をしていると、偶然、イシュマエル人の商人たちがそこを通りかかります。そこで悪知恵を働かせたのがユダです。「ヨセフをイシュマエル人に奴隷として売ろう」と提案します。当時、若い男の奴隷は高く売れましたから、せっかくなら殺さずに奴隷として売った方が得だと考えたわけです。とんでもない考えです。もしそこにルベンがいたら、間違いなく反対したはず。しかしこれまた偶然、ルベンはその場にいませんでした。止める人が誰もいなかった。結果、ヨセフはそのまま奴隷として売られ、エジプトへ連れて行かれます。弟を奴隷として売り飛ばす。起きてはならないことが起きてしまいました。
その後、お兄さんたちはヨセフの長服を雄やぎの血に浸して、それを父ヤコブのところに送り届けます。けれどもここでずる賢いのは、お兄さんたちは嘘を言ってはいないということです。「これを見つけました。あなたのこの長服がどうか、お調べください」。自分たちの口からは、ヨセフが死んだということを言いません。お父さんに自らそれを言わせている。父を騙すわけです。ここでもまた、私たちは罪の連鎖を見ます。かつて、ヤコブが父イサクを騙したように、今度はヤコブの息子たちが、父ヤコブを騙している。そしてヨセフが死んだと思ったヤコブは、深い、深い嘆きに囚われていく。罪に満ちた悲惨な世界です。
神の沈黙?
この悲惨な出来事を見る中で思うのは、神は何をしているのか、ということです。なぜ神さまはこの恐ろしい人間の罪の行為を止めないのか。神さまは一体どこにおられるのか。実際、ヨセフ物語全体を見ても、神さまが直接事に介入される、あるいは神さまのことばが直接人に語られることはほとんどありません。唯一、46章でヤコブがエジプトに下る決断をする際、神さまが夢の中でヤコブに直接語りかける場面が出てきますが、それだけです。神さまは基本、沈黙を貫いておられる。それがこのヨセフ物語です。
しかしだからこそ、このヨセフ物語は私たちの現実に訴えかけるものがあると思うのです。アブラハムやイサクやヤコブのように、神さまの声を直接はっきり聞くということはそうそうありません。もちろん、そういう経験をされた方はおられるかもしれませんが、少なくとも私は、そういった経験がありません。この先あるかどうかも分かりません。
では、神さまの声を直接はっきり聞いていないからと言って、神さまはそこにおられないと言えるのか。そうではないはずです。たとえ、神さまの声を直接耳で聞くことがなくても、神さまが直接介入されたとはっきり分かるような超自然的なことがなくても、あらゆる事柄の背後で確かに働いておられる神さまのお姿を私たちは知っています。先ほど、「偶然」ということばを何度も使いましたが、人の目では「偶然」と思えることも、神さまの前には実は「偶然」ではない。そこにも神さまの御手が働いている。様々な人間の営みが重なり合うこの世界。しかしその背後で、神さまがすべてを導いておられる。それが、このヨセフ物語のテーマです。教会はこれを「神の摂理」と呼んできました。
もちろん、神さまが背後ですべてを導いておられるからといって、人の罪の責任が問われなくなるわけではありません。ここで、お兄さんたちがヨセフに対してしたことは決して許されることではありません。聖書は徹底的に彼らの罪を暴き出しています。そしてこの後、彼らはその責任を問われていくことになります。人は、自らの罪の責任を取らなければならない。この原則が変わることはありません。
しかし、人間の罪によってどれだけ悲惨なことが起きようと、神さまのご計画が揺らぐことは決してありません。私たちを祝福で満たし、そして私たちを通してこの世界を祝福で満たすという神さまの救いのご計画が揺らぐことは決してない。最悪と思える状況の中にも、神さまは確かにおられる。神さまの御手がそこにある。
神の摂理
最後に、ヨセフ物語のテーマである「神の摂理」を美しいことばで言い表している信仰問答の一節をお読みして、説教を閉じたいと思います。これまでもご紹介したことがあると思います。『ハイデルベルク信仰問答』問27です。
問27 神の摂理について、あなたは何を理解していますか。
答 全能かつ現実の、神の力です。それによって神は天と地とすべての被造物を、いわばその御手をもって今なお保ちまた支配しておられるので、木の葉も草も、雨もひでりも、豊作の年も不作の年も、食べ物も飲み物も、健康も病も、富も貧困も、すべてが偶然によることなく、父親らしい御手によってわたしたちにもたらされるのです。
吉田隆訳『ハイデルベルク信仰問答』新教出版社、2014年、28-29頁
「すべてが偶然によることなく、父親らしい御手によってわたしたちにもたらされる。」今日私たちが読んだ創世記37章は、「あのミディアン人たちは、エジプトでファラオの廷臣、侍従長ポティファルにヨセフを売った」という文章で終わります。この悲惨な出来事のどこに、神さまの父親らしい御手があるのか、今日の時点ではまだ分かりません。人の目にはまだ分からない。しかし最悪と思えるこの状況の中にも、神さまは確かにおられる。神さまの御手は確かにそこにある。この摂理の信仰に立ちながら、この後のヨセフ物語をご一緒に読み進めていきましょう。その中で私たちは、この世界を治め、導いておられる、全能かつ現実の神の力を目にすることになります。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。