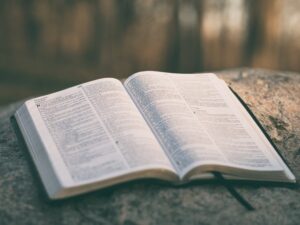詩篇90篇「自分の日を数える」
序
本日は召天者記念礼拝にようこそお越しくださいました。1年に1回、先に天に召された、愛する方々のことをおぼえ、いのちの主権者なる神さまを礼拝するひとときです。今日も、私たちの教会の召天者名簿をお配りしています。今年の名簿には新たにお二人のお名前、NさんとKさんが加わりました。この名簿にお名前が加わるということは、地上に残された私たちにとっては寂しいことですが、この方々のお名前は神さまに確かにおぼえられている、そのことに揺るがない慰めを得ていきたいと思います。
今日、私たちは聖書の詩篇90篇を開いています。詩篇というのは、信仰者の祈りと賛美のことばを集めた書です。全部で150篇からなっています。その中でこの90篇は、「死をおぼえて生きる」ということをテーマにした祈りになっています。そのテーマを最もよく表しているのが12節です。「どうか教えてください。自分の日を数えることを。/そうして私たちに、知恵の心を得させてください」。「メメント・モリ」ということばをお聞きになったことがあるでしょうか。ラテン語で「死をおぼえよ」という意味の格言です。「メメント・モリ」、この詩篇90篇が語っているのはまさにそうことです。私たちはどのようにして自分の日を数えて生きたらよいのか。どのようにして死をおぼえて生きたらよいのか。どうか教えてください。知恵の心を得させてください。天の神に祈り求めている。それがこの詩篇です。
いのちの主権
そこで、詩人がまず目を向けるのは、人のいのちの儚さです。3-6節「あなたは人をちりに帰らせます。/『人の子らよ 帰れ』と言われます。/まことに あなたの目には/千年も 昨日のように過ぎ去り/夜回りのひと時ほどです。/あなたが押し流すと 人は眠りに落ちます。/朝には 草のように消えています。/朝 花を咲かせても 移ろい/夕べには しおれて枯れています。」
人は古来、死を乗り越えようと様々な手を尽くしてきました。医学の発展は、そのおかげとも言えるでしょう。けれども、どれだけ医学が発達しようと、以前、死は変わることなく人の前に立ちはだかっています。死を免れる人は一人もいません。朝、花を咲かせても移ろい、夕べにはしおれて枯れてしまう。少し前まで元気だった人が、昨日まで元気だった人が、突然息を引き取るということが起こる。それは、決して他人事ではありません。すべての人は、今こうしてお話ししている私自身も、明日生きているかどうか、100%の保証はありません。人のいのちは儚い。私たちはみな、いずれ死を迎える存在です。
しかし詩人は、単に人のいのちの儚さをうたっているのではありません。詩人はそこに、いのちの主権者なる神さまを見ています。「あなたは人をちりに帰らせます。/『人の子らよ 帰れ』と言われます」。「自分のいのちは自分のもの」。多くの人はそう考えているかもしれません。しかし、そうではない。人は、いのちの主権者ではありません。他の人のいのちはおろか、自分自身のいのちの長ささえ決めることはできない。いのちの主権をもっておられるのは、この世界を造り、今も収めておられる、神さまただお一人です。私たちはこの事実を認めなければなりません。いのちの主権が自分にはないことを認める。そこで初めて私たちは、死をおぼえて生きる人生のスタートラインに立つことができます。
誇れるものは何もない
さて、詩人は人のいのちの儚さをおぼえる中で、自らが歩んできた人生を振り返ります。10節「私たちの齢は七十年。健やかであっても八十年。そのほとんどは、労苦とわざわいです。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります」。この詩が書かれた古代イスラエルでは、無事に成人した人は一般的に70歳、健康であれば80歳まで生きたようです。現代とそこまで大きな差はなかったということに驚きます。しかしいずれにせよ、詩人は「そのほとんどは、労苦とわざわいです」と語っている。ずいぶん悲観的です。さぞ苦労の多い人生を歩んだのだろうと想像します。
けれども、その前後の箇所を見ると、あることばが繰り返されていることに気がつきます。神の御怒りです。詩人は、自らの人生を振り返る中で、神の御怒りを強く意識している。神の御怒りというのは、感情的な怒りというよりも、正義を愛するがゆえに悪を憎まれる、神さまの義のご性質のことです。
なぜ詩人はここで、神さまの義を意識しているのか。自分の人生において、神さまの前に誇れることは何もないということを自覚しているからです。「神さま、私はこんな立派な人生を生きてきました!神さま、どうぞ見てください!」胸を張って言えるようなものは何もない。むしろ、神さまにはとても顔向けできないような人生を送ってきた。神さまの御怒りに値するようなことばかりしてきた。それが、労苦とわざわいに満ちた私の人生なのです。神さまの前に、自分の弱さを、自分の情けなさを、自分の罪深さを正直に告白している。詩人の正直な姿がここにあります。いのちの主権者である神さまの前で、決して自分を取り繕おうとしない。自分をよく見せようとしない。むしろ、「自分はこんなどうしようもない者なのです」、両手をあげて神さまに降参していく。その上で、詩人は祈るのです。「どうか教えてください。自分の日を数えることを。/そうして私たちに、知恵の心を得させてください」
神により頼む道
神さまを前にして、自らのいのちの儚さを認める。自らの人生に誇れるものは何一つないことを認める。ではその上で、私たちはどう生きていくのか。いくつかの道があります。一つは、快楽主義に走ることです。どうせ死ぬのだから、どう生きるかなんて考えずに、先のことなんか考えずに、今を楽しく生きよう。今この時の快楽を追い求めていく道。もう一方で、虚無主義の道もあります。どうせ死ぬのだから、もう何にも期待しない。この人生に意味などない。この人生に価値などない。ただ漫然と時間が過ぎ去っていくだけ。ただそれだけ。虚無に陥っていく道。
しかし、聖書が私たちを導こうとしているのは、そのどちらの道でもありません。聖書は、快楽主義でも、虚無主義でもない、第三の道を示していきます。それは、いのちの主権者なる神さまにより頼み、神さまの恵みのもとで喜び生きることです。13節から「帰ってきてください。主よ いつまでなのですか。/あなたのしもべたちを あわれんでください。/朝ごとに/あなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。/私たちのすべての日に/喜び歌い 楽しむことができるように。/どうか喜ばせてください。/私たちが 苦しめられた日々と/わざわいにあった年月に応じて。/みわざを あなたのしもべらに/ご威光を 彼らの子らの上に現してください。/私たちの神 主の慈愛が/私たちの上にありますように。/私たちのために 私たちの手のわざを/確かなものにしてください。/どうか 私たちの手のわざを/確かなものにしてください。」
詩人は分かっていました。いのちの主権者である神さまこそが、人の歩みに真の幸い、喜びをもたらしてくださるお方であることを。私たちが神さまの前に誇れることは何一つない。私たちにできるのはただ、神さまの恵みにより頼むこと。朝ごとに、あなたの恵みで私たちを満ち足らせてください。私たちの神、主の慈愛が、私たちの上にありますように。この世界のものに幸いを、喜びを求めていくのではありません。この世界のものは、結局は有限です。いつかは散っていく、儚いもの。そうではなく、永遠のお方である神さまに、真の幸いを、喜びを求めていく。祈り求めていく。それこそが、聖書の示す「死をおぼえて生きる」歩みです。
私たちの住まい
神さまに幸いを、喜びを祈り求めていく。この祈りが儚く散ることは決してありません。そこで最後に目を留めたいのは、1節のことばです。「主よ 代々にわたって/あなたは私たちの住まいです。」「住まい」とはどういう場所のことでしょうか。私たちが帰るところ、ほっと息をつけるところ、「おかえりなさい」と言ってくれる人がいる場所のことです。
教会では、この地上での生を終えられた方々のことを「召天者」と呼びます。天に召された者、神さまに呼ばれ、天に帰った者という意味です。この地上での歩みがどれだけ労苦とわざわいに満ちたものであっても、私たちには帰る場所がある。「おかえりなさい。よくがんばった。」両手を広げて、私たちを温かく迎えてくださる方がおられる。その確信があるから、私たちは死をおぼえて生きることができるのです。死をおぼえることは、絶望することではありません。私たちの住まいである、神さまに希望をもって生きることです。「どうか教えてください。自分の日を数えることを。/そうして私たちに、知恵の心を得させてください」。この詩人の祈りを、私たち自身の祈りとして、ともにささげていきましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。