ヘブル人10:19-22「大胆に聖所に入る」
序
今日は7月の第一主日ですので、年間目標に関連したみことばに聴いていきましょう。はじめに、年間聖句をみなさんで読みます。週報の表をご覧ください。「ですから、兄弟たち、私は神のあわれみによって、あなたがたに勧めます。あなたがたのからだを、神に喜ばれる、聖なる生きたささげ物として献げなさい。それこそ、あなたがたにふさわしい礼拝です。」(ローマ人への手紙12章1節)この聖句から、「礼拝の民として歩む」という目標を掲げ、1年間の歩みを送っています。
今日私たちが開いているのは、ヘブル人への手紙です。このヘブル人への手紙は、主にユダヤ人クリスチャン向けに書かれた手紙です。なぜそれが分かるかと言いますと、内容のかなりの部分が旧約聖書の知識を前提としているからです。今日の箇所もそうです。ここで使われていることばはほぼすべて、旧約聖書を背景にしています。特に、旧約時代の幕屋に関する知識が前提とされている。
幕屋の構造
そこで、今日は久しぶりにスライドを使って、幕屋の構造を簡単に説明したいと思います。(1枚目)まずはこれが、幕屋とその周りの外庭のイラストです。当時、イスラエルの民は荒野に住んでいたわけですが、彼らの宿営の真ん中にこの幕屋が作られました。
外の庭の部分には、一般の民も入ることができました。ただ、「聖所」と呼ばれる幕屋の中には、祭司しか入ることができませんでした。(2枚目)この聖所は全体が幕で覆われていて、外からは見えないようになっていました。祭司たちはこの中でいけにえをささげたり、お香を焚いたりしていました。
けれども、一般の祭司でさえ立ち入ることができないスペースがありました。それが、垂れ幕で区切られた一番奥の「至聖所」と呼ばれる部分です。ここが、幕屋の中心でした。この至聖所には「あかしの箱」、または「契約の箱」、「神の箱」と呼ばれる箱が置かれていました。出エジプト記を見ると、この「あかしの箱」の蓋の上から、神さまはイスラエルの民に語りかけると言われています。神さまが語りかけてくださる場所、それはつまり、神さまに一番近い場所を意味します。神さまは天に住んでおられるお方ですが、この地上にあっては、至聖所を通して、ご自分の姿を現してくださる。ここが神さまとの出会いの場でした。
ですから、ここには一般の民はおろか、普通の祭司も立ち入ることができません。祭司の代表である大祭司だけが、年に1回入ることを許されていました。しかも、ただでは入れません。大祭司は自分自身と民全体のためにいけにえを屠って、その血を振りかけることによって、罪のきよめを行わなければいけませんでした。血によってきよめられるというのは、血に魔術的な力があるからということでは決してありません。血はいのちを表しています。人が神さまに近づくためには、いのちの犠牲が必要であった。大きな、大きな、いのちの犠牲がなければ、人は神さまに近づくことができなかったのです。
聖なる神と罪人
私たちは、その感覚をもっているでしょうか。今日のヘブル書の箇所が語るように、私たちはイエス・キリストによって大胆に神さまに近づくことができるようになった。本当に感謝なことです。しかし、それが当たり前になっていないだろうか。自分自身に改めて問い掛けたい。この世界を造られた聖なる神さまと、罪に汚れた私たち人間。本来であれば決して相容れない存在です。
今、隔週で行っている有志の学び会では、歴代誌を読んでいます。前回は、ダビデが神の箱をエルサレムに運び入れようとした際、ウザという人が誤って神の箱に触れてしまった結果、その場ですぐに打たれて、命を落としたという話を読みました。罪に汚れた人間は決して、聖なる神さまに触れるどころか、近づくことさえできない。それが、私たちの本来の姿です。
その感覚を、私たちはあまりにも蔑ろにしてしまっているのではないか。よく、夫婦関係や家族関係などで、ずっと一緒にいると、相手の存在のありがたみがなくなってきて、感謝をしなくなると言われます。同じようなことが、神さまとの関係においても起きているのではないだろうか。神さまがともにいてくださる。私たちの祈りを聞いてくださる。私たちの心の中に住んでくださっている。当たり前になりすぎて、それがどれだけ幸いなことであるかを忘れてしまっているのではないだろうか。
ですから、旧約聖書を読むことは大事なのです。旧約時代を知らなければ、私たちはすぐに、自分が受けている恵みの大きさを忘れてしまう。神さまの恵みに対して、どんどん無感覚になっていってしまう。私たちは旧約聖書を読むことを通して、イエス・キリストの恵みをもっともっと深く知ることができるようになります。
新しい道を開いてくださったキリスト
今日の箇所がまさしくそうです。ここまでの話を踏まえて、改めて今日のみことばを味わいましょう。19-22節「こういうわけで、兄弟たち。私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して、私たちのために、この新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには、神の家を治める、この偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて、邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい水で洗われ、全き信仰をもって真心から神に近づこうではありませんか。」
旧約の背景を知っていれば、多くの説明はいりません。ここで言われている聖所とは至聖所のことです。一般の民は決して入ることができなかった。しかし、イエス・キリストが十字架で流された血によって、尊いいのちの犠牲によって、私たちは大胆に聖所に入ることができるようになりました。イエスさまご自身が、聖所の垂れ幕のように、聖なる神さまと罪人である私たちの間に立ってくださって、新しい道を開いてくださった。そのイエスさまは今も、偉大な大祭司として、「大丈夫。わたしがすべてを成し遂げたから、安心して、大胆に進んでいきなさい」、私たちを招いてくださっている。これが、イエス・キリストの恵みです。神さまが、イエス・キリストによって私たちにもたらしてくださった豊かな恵み。
聖餐が表すもの
この恵みを最もよく表しているものに、この後私たちはあずかります。聖餐です。聖餐の式文の中には、こういうことばがあります。「この聖餐にあずかる時、主は聖霊の働きによって私たち一人ひとりの内に親しく臨んでくださいます」。神さまが私たちの内に親しく臨んでくださる。これはまさに、至聖所が表している現実です。聖餐にあずかるとは、神さまのご臨在で満ちた至聖所に入っていくことである、そう表現することもできるでしょう。そこで私たちは何を記念するのか。イエス・キリストの犠牲の死を記念するのです。キリストのからだを表すパンと、キリストの血潮を表す杯。この尊いいのちの犠牲のゆえに、私たちは今、大胆に聖所に入ることができる。神に近づくことができる。この恵みを味わうのが聖餐です。
けれども、この恵みをより深く味わうために、私たちは自身の罪の現実を認めなければなりません。式文はこう続きます。「そのため聖餐にあずかる人は、神の御前に自分自身を深く吟味し、悔い改めと信仰をもってこれに臨んでください」。神さまの前に自分自身を深く吟味するとき、そこで私たちが見るのは、聖所に入るのにまったくふさわしくない、一人の罪人の姿です。こんな薄汚れた自分が、どうして神さまの前に立つことができるだろうか。そう認めざるを得ない私たちの現実がある。
しかし、イエス・キリストはそんな私たちのことを招いてくださるのです。式文は続きます。「愛する兄弟姉妹たち。主イエス・キリストを神のひとり子である救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼して、キリストのしもべとしてふさわしく生きる志のある者はすべて、この食卓に招かれています。たとえ罪のとがめや良心の呵責を覚えたとしても、それを覆って余りある神の恵みに信頼し、信仰をもって聖餐にあずかってください」。
神の恵みに信頼し、信仰をもって聖餐にあずかる。何を信じるのか。イエス・キリストによって、私たちの罪がすべて洗いきよめられていることを信じるのです。自分の罪の現実に目を奪われるのではなく、キリストの十字架の恵みだけを見つめて、信仰をもって聖餐にあずかっていく。大胆に聖所に入っていく。それが、22節で語られていることです。「心に血が振りかけられて、邪悪な良心をきよめられ、からだをきよい水で洗われ、全き信仰をもって真心から神に近づこうではありませんか。」キリストの十字架の恵みに信頼をして、全き信仰をもって真心から神に近づいていく。この後の聖餐のとき、キリストの恵みをいよいよ豊かに味わっていきましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。

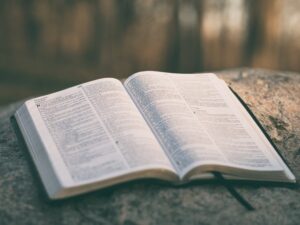
-e1752207370412-300x199.jpg)