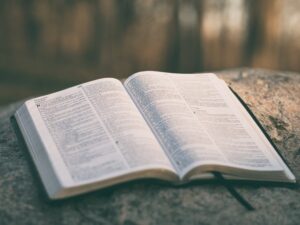創世記25:1-18「満ち足りた生涯」
序
アブラハムのこの地上での生涯が終わりました。齢175。8節には「アブラハムは幸せな晩年を過ごし、年老いて満ち足り、息絶えて死んだ」とあります。とても平和な終わり方です。波瀾万丈の生涯を送ったアブラハムでしたが、晩年は愛する息子イサクとともに、穏やかで幸せな日々を過ごした。そして葬りの際にはイサクだけでなくイシュマエルも駆けつけて、愛する妻サラと同じお墓に入れられる。素直に良かったなと思います。175年の長い人生、お疲れさまでした、と声をかけてあげたい。そんな思いがします。
傍系の系図
けれども今日の箇所を見ると、アブラハムの死と葬りを描く7-11節の前後に、イサク以外の子どもたちが出てきます。家系図で直系と傍系というものがありますが、ここで出てくるのはイサクから見た傍系の系図です。イサクの腹違いの兄弟たちの系図。これを見ると、なんとなくモヤモヤが残ると思うのです。まず、前半の1-4節では、アブラハムとケトラの間に生まれた子どもたちが出てきます。「アブラハムは一体何歳で子どもを生んだんだ」と思われるかもしれませんが、アブラハムがケトラを迎えたタイミングは、おそらくアブラハムがもっと若い頃、サラが存命中の頃だったと考えられます。サラが亡くなった後の再婚ではなく、サラの存命中に側女として迎え入れられたということです。当時の世界では一夫多妻制が一般的でしたから、アブラハムの行為も自然なこととして受け入れられていたのだと思います。旧約という時代の限界がここに表れています。
そこで、ケトラは子どもたちを何人か産むわけですが、やはり側女の子です。5-6節「アブラハムは自分の全財産をイサクに与えた。しかし、側女たちの子には贈り物を与え、自分が生きている間に、彼らを東の方、東方の国に行かせて、自分の子イサクから遠ざけた。」この「側女たち」には、ケトラだけでなくハガルのことも含まれます。おそらく当時の世界では、このアブラハムの対応は配慮あるものでした。側女の子にも贈り物を与えたとありますし、イサクから遠ざけたというのも、子どもたちを無用な後継者争いに巻き込まないためという意図があったと思われます。けれども現代の私たちからするとやはりモヤモヤが残ります。なぜ子どもの間に格差があるのか。みんな一緒に仲良く暮らすことはできなかったのか。
それは後半のイシュマエルの系図も同じです。18節の最後には、「彼らは、すべての兄弟たちに敵対していた」とあります。残念な結果です。アブラハムとサラがハガルとイシュマエルを追い出さなければ、こんなことにならなかったのに。とても残念に思います。
この後、聖書はイサクの子孫にのみフォーカスを当てていきます。ケトラの子どもたちの子孫、イシュマエルの子孫は物語の表舞台から消えていきます。旧約聖書はイサクの子孫であるイスラエルの民が残した書物ですから、当然と言えば当然です。けれども、やはりモヤモヤが残ってしまう。側女の子たちは、側女の子であるというだけで歴史から忘れ去られてしまうのか。
やがて一つの食卓に
人の目から見ればそうかもしれません。しかし、神さまの目には違います。まずはイシュマエルの子孫。16節には、イシュマエルの子孫が十二の氏族の長となったとあります。これは、以前神さまがイシュマエルに与えた祝福の約束の成就です。創世記17章20節にこうありました。「必ず、わたしは彼(イシュマエル)を祝福し、子孫に富ませ、大いに増やす。彼は十二人の族長たちを生む。わたしは彼を大いなる国民とする」。神さまは決してイシュマエルのことを忘れておられませんでした。イサクの直系にだけ祝福を注ぐのではなく、イシュマエルの子孫にも祝福を注いでくださっている。側女の子どもたちも確かに神さまの配慮のもとにあるのです。
また、新約の時代になると、神さまの祝福はイサクの直系、ユダヤ人だけでなく、全世界の民に広げられていきます。イエスさまは言われました。マタイの福音書8章11節「あなたがたに言いますが、多くの人が東からも西からも来て、天の御国でアブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓に着きます。」今日の箇所で、アブラハムの側女の子どもたちは各地へ散り散りになっていきました。けれどもそれは決して、彼らが神さまの祝福から追い出されるためではありません。ケトラの子孫も、イシュマエルの子孫も、東からも西からも、多くの人々が今や、イエス・キリストによって天の御国に招き入れられている。彼らも神さまの救いのご計画の中に確かに入れられているのです。
それは私たちも同じです。ケトラの子孫やイシュマエルの子孫はまだ傍系ですが、私たち日本人は傍系ですらありません。聖書の中には日本人の「に」の字も出てきません。けれどもそれは決して、神さまが私たち日本人を忘れておられるということではない。神さまは確かにこの東の果ての地、日本にも目を注いでくださっておられた。だからこそ宣教師たちを通して、この地に福音が、救いがもたらされたのです。昨日、私たちの教会を開拓したボーリン宣教師夫妻の娘さんお二人にお会いする中で、改めて私たちに注がれた神さまの祝福を確信しました。旧約の時代に散り散りになった民が、今、イエス・キリストによって一つとされている。一緒にアブラハム、イサク、ヤコブの食卓に着こうとしている。神さまの祝福の豊かな広がりをおぼえていきましょう。
アブラハムの生涯
さて、後半は、アブラハムの生涯の締めくくりについて考えていきましょう。175年の生涯。12章で神さまからの召しを受けてハランを旅立ったのが75歳の頃でしたから、カナンの地でちょうど100年過ごしたことになります。その間、様々な出来事がありました「あなたは、あなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、わたしが示す地へ行きなさい。」神さまのことばに即座に従い、カナンの地にやってきたアブラハム。しかしなかなか子どもが与えられずに悩み苦しむ日々。外国の王から自らの身を守るために、妻サラを妹と偽ったこと2回。甥のロトを救出するためにカナン連合軍と戦い勝利したこと。満天の星と、切り裂かれた動物を用いた契約の儀式、そして割礼によって、神さまの約束の確かさを改めて知ったこと。ハガルとイシュマエルを巡って板挟みにあったこと。御使いが訪ねてきたこと。ソドムとゴモラのために必死に執りなしたこと。そしてモリヤの地で、「アドナイ・イルエ」、主の山には備えがあることを確信したこと。
この波瀾万丈の生涯を送ったアブラハムの最期を、創世記は8節で「年老いて満ち足り」と表現します。「年老いて満ち足り」。旧約聖書の中で同じ表現が使われている人物には、イサク、ダビデ、ヨブ、そして第二歴代誌に出てくる祭司エホヤダがいます。エホヤダというのは、神さまに忠実な祭司として大変高い評価を受けている人物です。イサク、ダビデ、ヨブ、エホヤダ、そしてアブラハム。彼らは最後の最後まで、神さまの豊かな祝福に包まれて、この地上を去っていった。
確かな将来
こういった信仰者たちの晩年を思いながら、頭に浮かんでくる聖書のことばがあります。ご一緒に開きましょう。ヘブル人への手紙11章13節。これまでも何度かお読みしたことのある箇所です。「これらの人たちはみな、信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるか遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、寄留者であることを告白していました。」「あなたの子孫にこの土地を与える」、神さまからの約束を信じ、カナンの地に100年寄留したアブラハムでしたが、最終的に彼が手に入れた土地はサラを葬ったあの墓地だけです。約束のものを手に入れることはなかった。「彼は志半ばにこの地上を去った」という表現でもおかしくないはずです。しかし聖書はそれでも、彼の生涯は満ち足りたものであったと語ります。なぜか。あれが足りない、これが足りない、約束のものを手に入れていない今の現実ではなく、神さまは必ずこの約束を実現させてくださるという信仰に堅く立っていたからです。はるか遠くにそれを見て喜び迎えていた!
加藤常昭という牧師を以前にもご紹介したことがありますが、加藤先生はある本の中で、「未来」と「将来」の違いについて書いておられました。「未来」は「未だ来ていない時」と書きます。「未だ」の側面が前面に出ることばです。それに対して「将来」は、「将に来ようとしている時」と書きます。来るか来ないかではなく、今まさに来ようとしている。実現しようとしている。そこには確かさがあります。
アブラハムは、この「将来」、将に来ようとしている神の時を見つめていました。自分の目には未だ実現していない神さまの約束。しかしこの生涯を通して私に良くしてくださった神さまは、いつか必ずご自分の約束を果たしてくださる。私に注がれた祝福は息子イサクに受け継がれ、その先に必ず約束の実現が待っている。だからこそ彼は、約束のものをはるか遠くに見て、喜び迎えることができたのです。志半ばの生涯ではなく、神さまの約束の確かさを信じ、満ち足りた生涯を終えることができた。
ここに、信仰者の幸いがあります。一般に、「満ち足りた」と言えるような人生を送ることができるのは、社会のごく僅かの人々です。普通の人は、なかなか「満ち足りた」と確信をもって言うことはできないと思います。むしろ人生を振り返る中で、欠けたところばかりが見えてくる。あれが叶わなかった。これができなかった。心残りの数々。この地上の視点から見れば、確かに私たちの人生は欠けだらけです。「満ち足りた」とはなかなか言えない。
しかし、主を信じる信仰に立つとき、私たちは「満ち足りた」と確信をもって言える生涯を送ることができます。私たちの生涯は、この不完全な欠けだらけの地上では終わらないことを知っているからです。私たちには、イエス・キリストによってもたらされた新しいいのちが、復活のいのちが約束されている!それはまだ見ぬ「未来」ではなく、将に来ようとしている「将来」です。確かな将来。来週のイースターは、私たちに約束されているその確かな将来を改めておぼえる日です。この確かな将来が約束されているからこそ、私たちは今の地上にあって、「それを見て喜び迎える」ことができます。将来の希望を先取りして生きることができる。まことに「満ち足りた」人生を送ることができる。信仰者に与えられているこの幸いをおぼえながら、この地上を旅人、寄留者として最後まで歩み続けていきましょう。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。