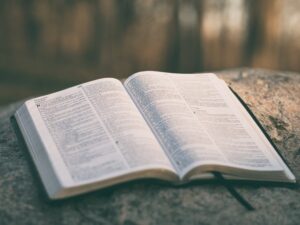創世記23:1-20「墓を訪れるたびに」
序
長く続いたアブラハム物語もいよいよ終盤です。この箇所に描かれているのは、アブラハムの妻、サラの死と葬りです。思い返せば、サラは非常に人間味あふれる女性として描かれてきました。夫の指示によって、二度も自らをアブラハムの妹と偽り、異国の君主に召し入れられるという経験。子どもが与えられない中、女奴隷ハガルを召し入れるよう夫に進言するも、ハガルとの関係が悪化し、妊娠中のハガルを家から一度追い出していく。御使いが訪ねてきた際には、来年の今頃には男の子が与えられているという約束を聞いて思わず笑ってしまう。その後、齢90にして待望のイサクが与えられるも、ハガル・イシュマエル親子との関係はいよいよ難しくなり、最終的に家から追い出していく。決して理想的な人物としては描かれていません。多くの欠けがある一人の人間、普通の人間です。しかし神さまはそんなサラを、神さまの約束を担う大切な家族の母として選び、祝福を注ぎ続けた。サラの生涯もまた、神さまの恵みとあわれみに包まれていました。
しっかり悲しむこと
そんなサラのこの地上での生涯は、127年で幕を閉じます。2節には、「アブラハムは来て、サラのために悼み悲しみ、泣いた」とあります。愛する人の死を前にして、悼み悲しみ、涙を流すアブラハム。私たちと変わらない、一人の信仰者の姿がここにあります。時折、「クリスチャンには天の御国の希望があるのだから悲しんではならない」、そんな声を聞くことがあります。しかし、それは誤りであると私は思います。もちろん、私たちには確かな希望が与えられています。しかしだからと言って、今の世での別れの悲しみがなくなるわけではありません。悲しいものは悲しい。あのイエスさまも、愛する友ラザロの墓を前にして涙を流した。ヨハネの福音書はそう証ししています。悲しみを抑え込み、悲しみを否定するのではなく、悲しみを正面から受け止め、悲しみを肯定する中で、私たちの心は少しずつ癒されていく。私たちの目は少しずつ希望へと開かれていく。「アブラハムは来て、サラのために悼み悲しみ、泣いた」。アブラハムの姿から、「しっかり悲しむ」ことの大切さを教えられます。
ヒッタイト人との交渉
「しっかり悲しむ」。その一つの大切なステップとして、「葬り」があります。けれども寄留者であるアブラハムには、サラを葬ることのできる土地がありません。そこでアブラハムは地元のヒッタイト人たちと交渉をしていくことになります。3節以降にやり取りが詳しく書かれていますので、ざっと流れを見ていきましょう。
まず、アブラハムは4節で、「あなたがたのところで私有の墓地を私に譲っていただきたい」と話をもちかけます。するとヒッタイト人たちは6節で、「私たちの最上の墓地に、亡くなった方を葬ってください」と提案します。アブラハムに対して「あなたは神のつかさです」と語りかけているのを見ても、アブラハムがいかに地元の人々からの信頼を勝ち得ていたかが分かります。
しかしアブラハムはその申し出に対して8-9節で、ツォハルの子エフロンが所有しているマクペラの洞窟を譲って欲しい、十分な額を払うから、ともちかけます。ヒッタイト人たちの墓地の一角の使用権が欲しいのではなく、土地そのものを買いたいのだという要求です。
すると10-11節で当のエフロンが出てきて、「いやいや、お金はいらないから、土地も洞穴も全部タダで差し上げます」と申し出ます。大変気前の良い申し出です。しかしアブラハムは礼を述べつつ、その申し出も断ります。プレゼントではなく、ちゃんと正規の値段で土地を買いたいのだと言うわけです。そこでエフロンは、「分かりました。それなら銀四百シェケルでどうでしょうか」ともちかけたところ、アブラハムはその申し出をそのまま受け入れて、交渉が成立します。そして大勢が見ている前で銀四百シェケルを支払い、無事に土地が手に入り、サラはその土地の洞穴に葬られていく。一件落着です。
ただ読んでいて気になるのは、なぜアブラハムは正規の値段で買うことにここまでこだわったのかということです。素直に好意を受け取ればよかったのに。しかもこの銀四百シェケルというのは実はかなりの額です。お金を払って買うにしても、もう少し交渉すればよかったのに。交渉が下手だな。思うかもしれません。
けれども、ここにはアブラハムの意図がありました。言ってしまえば、「ただよりも高いものはない」ということです。タダで譲り受けるということは、相手に対して大きな借りを作ることになります。するとどうなるか。これから先、アブラハムはエフロンやヒッタイト人たちに逆らえなくなるわけです。もし「やっぱり土地を返してください」と言われたら、返さざるを得なくなる。この先も土地を所有し続けることができる保証がありません。安心してサラを葬ることができない。だからアブラハムは正規の値段で購入することにこだわりました。しかも値切ってしまっては、「あのとき値切ってあげたんだから」と後から言われるかもしれませんから、相手が提示した額をそのまま受け入れて、誰も文句をつけようがない形で土地を所有しようとした。それがアブラハムの意図でした。
約束の確かな前進
さて、ここまで今日の箇所の流れを見てきましたが、この箇所は私たちに何を語りかけているのでしょうか。墓地の正しい入手方法を教えているのか。そうではないと思うんですね。土地をただで譲り受けることを聖書は禁じている、あるいは、交渉して値切ることを禁じている、そんなことは決してありません。そういうことを聖書は言おうとしているのではない。
では、一体この箇所は私たちに何を語ろうとしているのか。そこで思い出したいのは、神さまがアブラハムに与えた約束です。神さまはアブラハムを生まれ故郷から呼び出し、カナンの地に導いた後、「わたしは、あなたの子孫にこの地を与える」(12:7)と約束されました。この内、子孫が与えられるという約束は実現しました。不妊で苦しんでいたアブラハムとサラに息子イサクが与えられた。けれども、息子が与えられてもなお、アブラハムは土地をもたない寄留者のままです。「この地を与える」という神さまの約束は一体いつ実現するのだろうか。アブラハムは思っていたはず。
そんな中で記されているのが今日の箇所です。アブラハムが初めて正式に所有した土地、それは妻サラを葬るための墓地でした。アブラハムはここで一体何を感じ、何を思ったでしょうか。人の命ははかない。限りがある。この自分も、まもなくサラの後を追うことになるだろう。しかしそれは決して、神さまが私たちを見放したということではない。神さまの約束がなくなったということではない。サラの死と葬りを通して初めて土地が与えられたように、神さまの約束は確かに前進している。自分たちはこの地上を去ることになるけれども、神さまご自身が与えてくださった息子イサク、そしてその子孫たちを通して、神さまは必ず約束を実現させてくださる。アブラハムにとってこの墓地は、サラを失った悲しみ、寂しさをおぼえる場所であるのと同時に、自分たちの子孫を通して実現する神さまの約束への希望をおぼえる場所になったはずです。
希望を証しする場所
今の時代、お墓はいらないと考える人が増えています。ある会社が行った20代以上の男女500人に行ったアンケートによれば、「墓じまいをしたいと思うか」という質問に対して、「とても思う」「やや思う」と答えた人は全体の約70%にも及んだそうです。理由として一番多かったのは、「維持管理・墓参りが大変」ということでした。確かにそうです。私たちの教会でも、近隣の4教会合同で納骨堂と合葬場所をもっていますが、やはり維持するのは大変です。昨年末も緊急に修理が必要な箇所が見つかり、すぐに業者にお願いしたということがありました。建て替え、リフォームについても納骨堂委員会で話し合い続けています。お墓をもつというのは大変なことです。
けれども納骨堂委員会で繰り返し確認しているのは、維持管理がどれだけ大変でも、私たちはお墓を大切にし続けるということです。個人でお墓をもたない人が増えているからこそ、教会はお墓を大切にし続けたい。なぜか。墓は、愛する人を失った悲しみを共有する場であるのと同時に、キリストにある復活の希望を証しする場でもあるからです。
教会には、様々な式の手順や祈りの文言がまとめられた『式文』というものがあります。その中から、「埋葬式・納骨式」の際にささげる祈りのことばの一部をここでご紹介します。祈りの最後の部分です。
〇〇兄弟/姉妹を主のもとに送った私たちは、なおしばらくの間、地上の旅路を歩むことになります。
どうか、主にあって天に望みを置き、神の栄光を仰ぎ見て生きることができますよう支えてください。
そして、この墓を訪れるたびに、故人の在りし日を偲ぶとともに、永遠の御国をはるかに望みつつ、主の日に備えさせてください。
主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
「この墓を訪れるたびに、故人の在りし日を偲ぶとともに、永遠の御国をはるかに望みつつ、主の日に備えさせてください。」私たちは愛する人が眠るお墓を訪れるたびに、愛する人と過ごした日々を思い起こします。けれどもそれだけではなく、その愛する人は今も神さまの御手の中にあることを思い起こす。そして、イエス・キリストが十字架にかかり葬られた後、三日目によみがえられたように、その愛する人も、そして私たち自身も、イエスさまが再び来られるとき、必ず復活の恵みにあずかることに希望をもっていくのです。
私たちの教会の納骨堂の名前は「きぼうの園」です。納骨堂の正面部分にある聖書のことばが記されているのをみなさんはご存知でしょうか。「我は復活なり 生命なり」(ヨハネ伝11:25)そう記されています。これは文語訳聖書のことばですが、11章25節には続きがあります。「我を信ずる者は死ぬとも生きん」。現代語に直すと、「わたしを信じる者は死んでも生きるのです」。イエス・キリストを信じる者は死んでも生きる。私たちはあの納骨堂を訪れるたびに、このイエスさまの約束を思い起こし、希望を新たにしていくのです。だからこそあの場所は「きぼうの園」と名付けられています。
「アブラハムは来て、サラのために悼み悲しみ、泣いた」。愛する人の死は、辛く悲しいものです。けれども私たちはこの悲しみと正面から向き合うことができます。悲しみの先にある確かな希望を信じているからです。この悲しみは悲しみで終わらない。いつか必ず、神さまご自身が私たちの目の涙をことごとくぬぐいとってくださる。喜びに満ちあふれた、新しい天と新しい地が私たちに用意されている。この神さまの約束に立ち続けていきたいのです。墓を訪れるたびに、この希望に目を向けていきたい。神さまの約束は今も確かに前進しています。
※説教中の聖書引用はすべて『聖書 新改訳2017 ©2017 新日本聖書刊行会』を用いています。